ここ数年、自治体での導入が増えている「デマンド交通」。利用者にとって利便性が高い一方、導入に際しては事前の検討が欠かせません。
本記事では、デマンド交通の仕組みや導入時に確認しておきたい点について整理します。
デマンド交通の概要
デマンド交通(Demand Responsive Transport:DRT、需要応答型交通)は、路線バスとタクシーの中間に位置する公共交通サービスです。あらかじめ予約を受けて運行し、発着地や時間を柔軟に設定できるのが特徴です。
タクシーとの違いは、車両にバスを利用できることや、複数人で乗り合いが可能である点にあります。平成18年の道路運送法改正により、乗合事業の一形態として位置づけられました。
導入による利点
デマンド交通を導入することで、次のようなメリットが期待できます。
-
移動手段を確保できる
- 鉄道やバスが整備されていない地域では、生活に必要な移動を支える手段となります。都市部でも高齢者の買い物や通院の際に役立ち、日常生活を支える重要なインフラとなります。
-
輸送コストを抑えられる
-
利用者が少ない地域でコミュニティバスを走らせると、空気を運ぶような非効率な運行となり、コストがかさみます。必要なときだけ運行するデマンド交通なら、その無駄を抑えることが可能です。
-
-
運行ルートを柔軟に設定可能
- 事前に停留所やルートを決めておき、予約に応じて効率的に運行する方法もあれば、エリア内で自由にドアツードアの運行を行う方式も選べます。
導入にあたって検討すべき点
デマンド交通を導入する際は、以下の点を明確にすることが重要です。
-
導入の必要性
地域の状況によっては、デマンド交通よりもコミュニティバスのほうが適している場合があります。利用者数や需要の集中具合を見極め、他の交通機関と比較しながら、デマンド交通を選ぶ理由を整理しましょう。
-
予約システムの形態
予約はITシステムで一括管理する方法と、電話受付を中心とする方法があります。IT化は効率的ですが高齢者には使いづらい面があり、電話対応は利用者に優しい反面、人員配置のコストがかかります。地域の特性に合った仕組みを選ぶ必要があります。
-
対象者や車両の設定
利用対象を高齢者や住民に限定することも可能で、その場合は登録制や利用券の導入なども検討されます。車両は小型車から大型バスまで柔軟に選択でき、利用状況によって複数台を用意することも必要です。外装でデマンド交通であることを分かりやすく示すことも重要です。
運行業務の委託について
多くの自治体では、予約受付や配車、運行業務を専門事業者に委託しています。費用だけでなく、以下の視点で業者を選ぶことが欠かせません。
-
予約、運行システムの信頼性
-
効率的な運行には、予約内容を正確に管理し、最適なルートを選択できるシステムが不可欠です。利用者にとっても操作しやすい仕組みであるか確認しましょう。
-
-
安心して任せられる体制
- 運転手の接遇や労務管理、健康管理が徹底されているかは重要なチェックポイントです。さらに、車両の点検体制や緊急時の対応能力も評価対象となります。
-
運行管理の実績
- 過去の運行実績、事故の有無、他分野での輸送経験などを確認することで、信頼できる業者かどうか判断できます。
まとめ
デマンド交通は、公共交通が不足する地域で住民の移動を支える有効な手段です。柔軟な運行やコスト削減といった利点がある一方、導入目的を明確にしないと利用が伸びず、負担ばかり増える可能性もあります。
成功させるには、地域の特性に合った予約システムを整え、信頼できる運行業者を選ぶことが重要です。利用者にとって分かりやすく、安全で使いやすい仕組みを築くことで、地域に根付く交通手段として継続的に機能していきます。
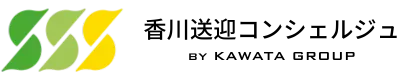











コメント