近年、少子化や共働き世帯の増加により、子どもの安全確保や保護者の負担軽減を目的に「送迎サービスの有無」が保育園を選ぶ際の重要な基準になってきています。
しかし現状では、送迎バスの運転を保育園の職員が担当しているケースも多く、人員不足が続く園にとって大きな負担となっています。さらに、新たにドライバーを確保しようとしても、採用活動に手が回らない園も多く、人材の確保は簡単ではありません。
本稿では、送迎バスを運行する園が直面している課題と、それらを解決する手段の一つとして注目される「送迎業務の外部委託」の利点について整理していきます。
保育園における送迎バス運行の現状
保護者にとって、自宅から距離のある園に子どもを通わせる際には、通園バスがあるかどうかが大きな判断材料になります。しかし、社会福祉法人日本保育協会の調査では、全国の保育園・認定こども園のうち通園バスを運行している割合は18.8%にとどまっています。
この割合が低い背景には、人員・コスト・安全面の課題があると考えられます。
保育園が直面する主な課題
慢性的な人材不足
厚生労働省の調査(2020年9月)によると、保育士の離職率は約9%。有効求人倍率も同年7月時点で2.29倍と、全職種平均(1.05倍)を大きく上回っています。業務量が膨大であることや処遇面の問題が退職理由として挙げられており、慢性的な人材不足は今も解消されていません。
送迎業務による負担とリスク
多くの園では、送迎バスの運転を職員や園長が担っています。通常業務に加えて運転業務も行うことは大きな負担であり、確認不足から園児が車内に取り残される事故も実際に起きています。安全確保が最優先である以上、送迎業務を専門事業者に委託することは有効な手段といえます。
通園バスに使用される車両と免許
通園バスは主に以下の2種類に分類されます。
-
小型幼児送迎バス:大人2人+幼児12人程度(ワゴン・小型バス)
-
中型幼児送迎バス:大人3人+幼児39人程度(マイクロバス)
さらに大人数の送迎が必要な場合は、大型バスが使われることもあります。
運転に必要な免許は以下の通りです。
-
普通免許:大人定員10人まで
-
中型免許(限定解除):大人定員29人まで
-
大型免許:すべての通園バスに対応
送迎人数に応じて適切な車両を準備し、免許を持つ人材を確保する必要があります。
通園バス運行に伴う主な経費
通園バスの運行には、以下のようなコストが発生します。
-
車両購入やリース代
-
ドライバー・添乗員の人件費
-
燃料費
-
駐車場代
-
税金(自動車税・重量税など)
-
保険料(自賠責・任意保険)
園の環境によっては、これ以外にも維持費がかかる場合があります。
送迎代行サービスを利用する利点
車両管理や清掃を委託できる
バス運行には、送迎だけでなく日常的な点検や清掃が不可欠です。感染症対策も含めて、委託業者に任せることで園の負担を軽減できます。
ドライバー確保の心配が不要
職員の欠勤などで急に代わりの運転手を探す必要がなく、委託業者がシフト管理や代替要員の手配を担います。
安全性の向上
委託業者はドライバーに定期的な研修を実施し、車両にはドライブレコーダーを設置するなど事故防止に取り組んでいます。
採用や労務管理の削減
ドライバーを自ら採用すると、募集広告や面接、勤怠管理などの事務作業が発生します。委託すればこれらを省略でき、人件費や時間を削減できます。
事故対応を委ねられる
万一事故が発生した場合も、対応は業者が行います。代車を手配してもらえるケースもあり、園側の業務中断を最小限に抑えられます。
まとめ:保育士の負担軽減と安全確保のために
保育園における送迎業務は、人員不足や安全面の課題から自園での対応が難しくなりつつあります。送迎代行サービスを利用することで、送迎・車両管理・ドライバー確保・事故対応といった幅広い業務を委託でき、保育士が本来の業務に専念しやすくなります。
費用負担は発生しますが、保育士の離職防止や子どもの安全確保といった観点から考えれば、長期的に見て有効な選択肢となるでしょう。園の現状や将来の運営方針を踏まえ、外部委託の活用を検討することが求められています。
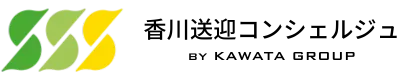





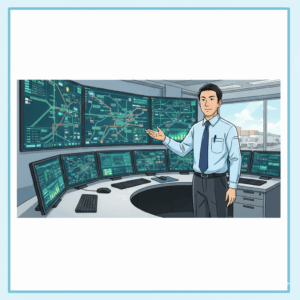





コメント